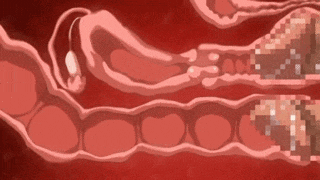ウンコう日誌(第824号)

大阪民国・害吉鉄道。
大阪ユニオン駅と芦原橋(本社前)を結ぶウンコう区間の朝は、いつも煤と湿った潮の匂いが混じっている。
その中を、今日も木炭動車107号は、青いレールの上をゆっくりと転がっていた。
屋根の上には、無理やり積まれた木炭箱。
本来なら森林鉄道か山奥の簡易線に押し込められるはずの代物だが、害吉鉄道ではまだ「現役」だ。
「오늘도 연기 많네ぇ…」
「冇办法啦、炭少ないねん」
「老板又言っとるで、“这是最先进的内燃技术”やて」
車内では、大阪弁と韓国語と中国語が、煤と一緒に漂っていた。
誰も本気で「最先端」だとは思っていない。だが、動く。それだけで十分だった。
芦原橋(本社前)を出ると、線路脇の景色は一気に荒れる。
倉庫、ドラム缶、壊れたクレーン、そして住み着いた人間たち。
木炭動車は速度を落とし、息を整えるように、ゴト…ゴト…と音を立てる。
運転台では、年季の入った運転士が炭の量を確認していた。
「あと一往復はいけるな」
「釜ヶ崎まで持つ?」
「持たせるんや。持たんかったら、ここで焚く」
論理はいつも逆だ。
目的地があるから燃やすのではない。
燃やせるから、目的地がある。
途中、堀江新地の簡易ホームで数人が乗り込む。
顔色の悪い若者、言葉の通じない男、国籍不明の女。
誰も行き先を聞かない。聞く必要もない。
「釜ヶ崎?」
「…嗯」
「ほな乗り。钱あとでええ」
木炭動車は再び走り出す。
ディーゼルカーが嫌うこの区間を、あえて選ばれた存在のように。
やがて、遠くにコンクリ桟橋の影が見える。
世界中から流れ着いた混沌の終点であり、次の始点。
その少し手前で、木炭動車は一度、大きく咳き込む。
煙が濃くなり、速度が落ちる。
「あかん、炭が湿っとる」
「昨日雨やったからな」
「でも止まらんで。害吉や」
誰かが笑い、誰かが咳をする。
そして木炭動車は、また走り出す。
この鉄道は、過去の亡霊の寄せ集めだ。
だが、害吉鉄道ではそれが「日常」だった。
今日もまた、時代に取り残された木炭動車が、
大阪民国の底辺を、確かに運んでいく。
――煙と一緒に、人間を。