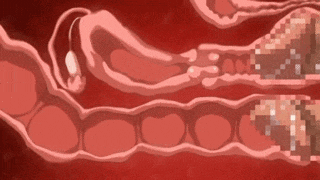ウンコう日誌(第800号)

芦原橋のヤードに、夕方の汽笛がかすかに響く。
冬の冷たい風が、石炭でも重油でもない、どこか甘い木炭の匂いを運んでくる。
107号は古い木炭動車だった。
燃料タンクのかわりに積まれた木炭箱を、朝いちばんに点火して暖めるのが日課だ。
運転士の張(チャン)さんは、まだ若いのに腕が立つ。「この子は生き物だ」といつも言う。
点火がうまくいかない朝には、煤で顔を黒くしながら「まあ、こいつも眠いんや」と笑っていた。
今夜は釜ヶ崎行きの最終列車。
積荷は少ないが、乗客の目は皆どこか疲れている。
工場帰りの労働者、古びたコートの女、荷物だけを抱えた旅の男。
木炭の火が赤く揺れるたび、客室の中は淡いオレンジ色に染まり、誰もが無言のまま暖を取った。
堀江新地を過ぎると、張さんがそっと話しかけた。
「兄弟(ブラザー)、お前、まだ走りたいか?」
もちろん返事はない。けれど107号の床下から、ぼうっと音を立てて木炭の火が強くなる。
それを見て張さんは笑った。「そうか、まだ走りたいか。」
夜の釜ヶ崎駅。
ランプの灯だけが雪の粒を照らす。
107号は静かにホームに滑り込み、息をつくように停まった。
降りる者も、迎える者もほとんどいない。
ただ駅の向こうで、誰かが小さくギターを弾いている。
張さんは運転台の窓を開け、冷たい空気を胸いっぱいに吸い込んだ。
「ええ夜やな。明日も走ろか、107。」
木炭の煙は、夜空の星に溶けていった。
どこか懐かしい、昭和の匂いを残して。