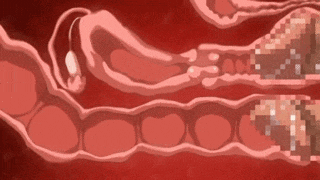ウンコう日誌(第788号)

害吉鉄道の朝は、いつも薄曇りから始まる。
大阪ユニオン駅の片隅で、古びた木炭動車107号が、ゆっくりと煙を吐いていた。
エンジンの代わりに木炭炉がごうごうと燃え、運転士のキム・ハンスがトングで炭をかき混ぜる。
「오늘도 가자, 콘크리부두까지(今日も行くで、コンクリ桟橋まで)」
沿線には芦原橋本社前、釜ヶ崎、北津守、南津守、そして果てのコンクリ桟橋。
線路の両側には、世界のどこにも似ていない大阪民国の混沌が広がっていた。
干からびた洗濯物、壊れた自転車、バラックの間から流れてくるアジア諸語のミックスサウンド。
駅舎のベンチでは、行き場をなくした労働者たちが黙って煙草を吸っている。
「次の釜ヶ崎行き、まもなく発車します」
構内スピーカーはもう壊れて久しい。代わりにホームの男が、口で叫ぶ。
木炭の匂いが、焼けた油と汗の匂いと混ざって車内に充満する。
107号の窓からは、異国の旗と看板が入り乱れた堀江新地の裏通りが見える。
車体の緑色は褪せ、しかし誇らしげに「害吉鉄道」のエンブレムを光らせていた。
「이게 마지막 세대야(もうこれが最後の世代や)」
車掌の陳さんが、懐中時計を見ながらつぶやく。
石炭もガソリンも入らぬこの国で、まだ木炭を燃やす車両が動くのは奇跡だった。
やがて、港の潮風が鼻を刺す。
コンクリ桟橋駅。
ここから阪琉航路と阪鮮航路が出る。
桟橋には、どこの国とも知れぬ難民船と、夢を諦めた人々が並んでいた。
107号のエンジンが止まり、車内に静寂が訪れる。
木炭の灰が舞い上がり、まるで雪のように床を白くした。
「次、帰れるんいつやろな」
ハンスが笑う。
「帰る国、もう無いんちゃう?」
陳が返す。
二人の笑い声が、遠くで鳴る汽笛と混ざった。
それが、害吉鉄道の朝の音だった。