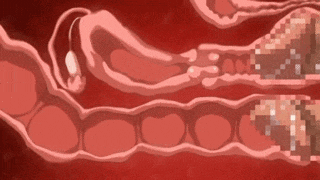ウンコう日誌(第780号)

C56 160号機。かつては泰緬鉄道の酷暑と密林を走り、数え切れぬほどの兵站と人命を背負った。ジャングルの鉄橋を渡り、赤土の築堤を喘ぎながら越え、蒸気のたびに熱風と絶望を吐き出してきた。
その小さなボイラーに詰め込まれていたのは、石炭と水だけではなかった。汗、血、涙――そして帰れなかった者たちの声だ。
戦後、奇跡的に日本へ戻されたこの機関車は、ひっそりと辺境の線区に配属された。誰も口には出さぬが、乗務員たちは「戦争を知っとる汽車」と呼んでいた。
その顔はどこか憔悴していたが、レールの上を走る時だけは誇りを取り戻すかのように煙を吹き上げる。
やがて害吉鉄道に払い下げられたC56は、芦原橋のヤードに据えられた。
大阪ユニオン駅から流れ込む労働者を、あるいはコンクリ桟橋に漂着する異国の人々を、釜ヶ崎へと運ぶ。かつては戦場で捕虜や兵を運んだが、今は敗戦都市の最底辺を黙って乗せるのだ。
「えらい汽車やな……」
大阪クレオールで囁く声がある。
「命、呑み込んできたんやろ」
煤で黒光りする小さな機関車は答えない。ただ笛を鳴らし、夜のガード下にこだまする。
それは鎮魂か、それとも生き延びた証か。
害吉鉄道の終着駅・コンクリ桟橋で、潮風を浴びながら静かに停まるC56の姿は、時代に取り残されながらもなお走り続ける「記憶の機関車」だった。