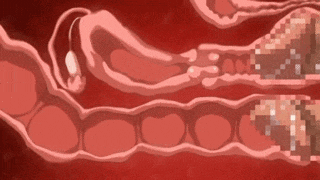ウンコう日誌(第773号)

大阪ユニオン駅の片隅。
煤けた緑色の蓄電池動車107号が、闇の中で唸りを上げていた。屋根には使い古された煙突、側面は傷だらけ。鉛電池を抱え込みながら、辛うじて走り続ける害吉鉄道の古参車両である。
「おい兄ちゃん、これ釜ヶ崎行きやろか?」
「せやせや、まちがいないで。はよ乗らんと席なくなるでぇ」
関西訛りにまじって、広東語やクメール語が飛び交う。
「快啲啦!」「Cepat cepat!」
荷物を抱えた労働者たちが、我先にと乗り込んでいく。
車掌が慌ただしく走り回りながら叫ぶ。
「バッテリー今日いけるんかいな?」
「しらんわ、昨日は途中で電池切れてみんなで押したんや!」
「아이구… ほんまシャレならんで」
発車の鐘が鳴ると、車両はぎくしゃくと動き出す。窓の外は真っ暗、工場の煙と湿った空気が車内に流れ込む。
「おっちゃん、どこから来たん?」
「長崎からや。ユニオン着いたら即これや。カネも無いしな」
「ほな、釜ヶ崎で一緒に泊まろや。飯は安うてうまいとこ、わし知っとるで」
「그거 좋지!」
蓄電池はうなるような音を立てながら、芦原橋(本社前)へ、そしてさらに釜ヶ崎へと列車を押し出す。
車内は汗と酒の臭い、炊き出しの味噌汁の匂い、笑い声と怒鳴り声が混ざり合い、まるで世界の終わりを先取りしたかのようだった。
終点、釜ヶ崎駅。
薄暗いホームに降り立った乗客たちは、疲れ切った顔をしながらもどこか安心した表情を浮かべていた。
「ここが釜かいな……」
「そうや。ここ来たらもう、どこから来たんかも関係あらへんのや」