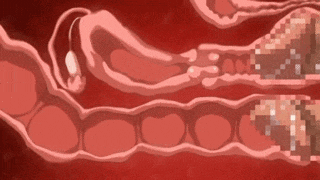ウンコう日誌(第769号)

大阪民国の片隅、害吉鉄道の青い線路を、ちんまりとした緑の木炭動車が走っていた。車体に刻まれた「107」の番号は、すでに数十年前から現役を続けてきた証だった。
木炭をくべる煙突は小さく、しかし運転士の手際で火は絶やされることなく赤々と燃え、車両の横腹に据え付けられた小さな炉からはじんわりとした熱が漏れていた。ガソリンも電気も安定供給されない大阪民国では、むしろこの木炭動車が一番確実に走るのだった。
「아재, 오늘도 가마가사키 가는 거야?」
「せやで。釜ヶ崎まで民工(ミンコン)ぎょうさん乗せなアカン。」
車内では大阪クレオールが飛び交う。東南アジアから来た若者、朝鮮から渡ってきた労働者、そして日本各地の農村から仕事を求めて流れてきた者たち。彼らは擦り切れたカバンを抱え、狭い座席やデッキに身を寄せていた。
芦原橋(本社前)を過ぎると、動車はがくんと揺れながら南へ折れ、煤煙混じりの匂いを撒き散らしつつ釜ヶ崎へと突き進む。沿線の子どもたちは、石ころを手にしながらも、この木炭動車にだけは「アホ汽車や!」と笑い声を浴びせるだけで石を投げなかった。働きに出ていく父や兄が、このちっぽけな動車に揺られていくのを知っていたからだ。
コンクリ桟橋に世界中から流れ着く労働者がいるなら、大阪ユニオン駅から釜ヶ崎に吸い込まれていくのは日本の民工たち。木炭動車107号は、時代遅れの煤けた車体でありながら、まさに大阪民国の混沌をつなぐ生命線だった。
その夜、木炭炉に残る灰をかき出しながら運転士は呟いた。
「電気でも、ディーゼルでもアカン。結局、炭こそがこの街の血の色や。」
煤にまみれた107号は、翌朝もまた、釜ヶ崎へ向けて走り出す。