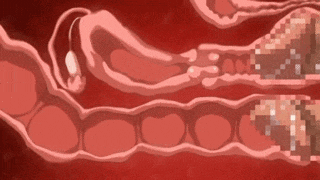ウンコう日誌(第765号)

コンクリ桟橋から遠く離れた「堀江新地」の片隅に、木賃宿や飲み屋の影にひっそりと「南堀江口駅」がある。そこに停まっているのが、害吉鉄道の蒸気動車107号。
見た目は市電の小型電車のようだが、屋根には煤けた煙突が突き出し、車内の一角には小さなボイラーが据え付けられている。石炭の代わりに、燃料は木炭や時には流れ着いた廃材。煙は甘ったるい匂いを漂わせ、乗客の衣服にまで染み込む。
この107号は大阪ユニオン駅から芦原橋(本社前)を経て、釜ヶ崎へ向かう列車。
朝一番、九州からの出稼ぎ労働者が夜行列車でユニオン駅に着くと、彼らは皆この蒸気動車に押し込まれる。車内は狭く、吊革もなく、荷物は天井に積まれ、煙と汗で視界が曇る。
駅舎の前では、荷役人が荷物を放り投げ、立ち食いの屋台からは沖縄ソバやビリヤニの匂いが混じって漂う。ホームの隅で所在なげに立つ者は、明日から建設現場へ赴くか、それともその日暮らしの運命か。
しかし、乗り合わせた者同士が言葉を交わすうちに、列車は異様な連帯感を生む。薩摩弁、博多弁、東北訛り、沖縄語、片言のタガログ語、韓国語が飛び交い、煙に包まれた車内はまるで一つの縮図。
「おーい、今日はどこの現場や?」
「釜の寄場や。運が良けりゃ日銭が出る」
蒸気動車107号は軋むような音を立てながら、ガタゴトと釜ヶ崎へ進む。車体は小さく、線路も古いが、乗客たちにとっては「仕事への通り道」であり、また「カオスな大阪民国の象徴」でもあった。
そして夕刻、107号は再びユニオン駅へ戻る。昼間に稼いだわずかな銭をポケットに握りしめ、また煙にまみれながら。
今日も明日も、彼らを運ぶのは、この小さな蒸気動車なのであった。