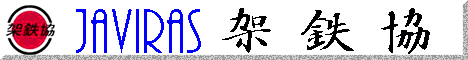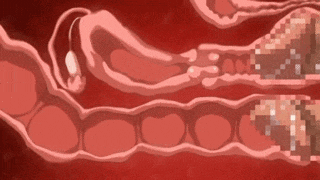ウンコう日誌(第764号)

かつて帝国の北辺を走っていた貨物用機関車D51は、戦後に樺太ごとソ連に引き渡され「Д51」として酷使された。極寒の地で薪も石炭も足りず、やがては泥炭や伐採残材を焚き、車体は煤と氷で真っ黒に覆われた。ソ連の整備工場では雑に補修され、側面にはキリル文字が打刻されたまま放置されていた。
時代が変わり、廃車同然となったこの機関車は密かに大阪民国へと持ち込まれる。港で荷を解いた瞬間から、その姿は「異国の呪物」のように港湾労働者をざわつかせた。害吉鉄道は「どうせ壊れても同じこと」と、このD51を釜ヶ崎行きの貨物列車に充てたのである。
大阪ユニオン駅からは九州・東北・北海道から流れてきた民工を満載し、コンクリ桟橋からはソ連経由で漂着した朝鮮人、中国人、さらにはアラブ商人までが雑居の貨車に押し込まれる。屋根の上ではインド系の労働者が香辛料の鍋を煮、車内では沖縄の民工が三線を鳴らす。
漆黒の「樺太帰りのD51」は、シベリアの寒気をまとったまま大阪民国の湿った空気を切り裂き、芦原橋のスイッチバックを越えて釜ヶ崎へと滑り込む。その煙突から吐き出される黒煙には、凍土の記憶と、国境を越えて流れ着いた無数の労働者の怨嗟が混じっているとさえ噂された。
鉄道帝を自称する害吉鉄道の社長は、このD51を見て「大東亜を越え、大シベリアすら我が路盤に収めた証」と豪語したが、実際は錆と油漏れだらけの老朽機。だが、このカオスの国には、そんな矛盾こそが似つかわしいのであった。