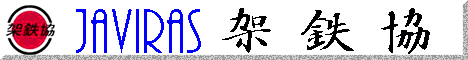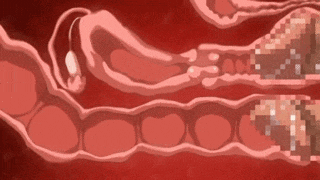ウンコう日誌(第763号)

害吉鉄道の片隅、堀江新地から釜ヶ崎に向かう短い区間を、今なお走り続ける古い木炭動車がある。車体番号107。
戦時中の燃料難に対応するために作られたこの車両は、石炭やガソリンが手に入らぬ時代に、山から切り出した木を炭に変えて走らせた。時代遅れの産物として忘れられてもおかしくなかったが、大阪民国の混沌はこの小さな車両を生き延びさせた。
朝、大阪ユニオン駅に列車が着くと、北九州や鹿児島から流れついた日雇い労働者たちが、この木炭動車に押し込まれる。煤けた排気をまき散らしながら、動車は南へ進む。窓の外には、コンクリ桟橋からやって来た貨物列車、蒸気動車、蓄電池動車が交錯し、アジアのラゴスと呼ばれる街のざわめきが広がる。
釜ヶ崎に着けば、乗客は一斉に降り、炊き出しへ、寄せ場へ、あるいは安酒場へと散っていく。木炭動車107号は短い休憩をとり、駅前で木炭を継ぎ足され、再び走り出す。車掌は「まだこの車も走れまっせ」と胸を張るが、誰もそれを誇りとは思わない。ただ、必要だから走っているのだ。
時代から見放され、だが都市の混沌に支えられて残る車両。木炭の匂いと共に揺れる107号は、今日もまた大阪民国の片隅で、人々の暮らしを黙って運んでいる。