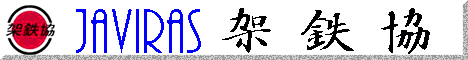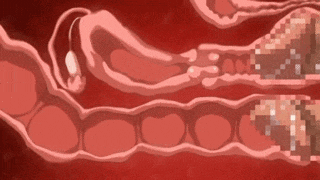ウンコう日誌(第757号)

「この線、昔は貨物列車が5分おきに通ってたんや。」
コンクリ桟橋の片隅で、静かに待機する木炭動車107号。くすんだ緑のボディ、煤けた屋根、そして側面の“107”の番号。その姿は、戦時中の記憶を今に伝える生きた遺物だ。
この車両が造られたのは、大東亜戦争も中盤の頃。石油はおろか、石炭も入らず、頼れるのは木炭だけだった。害吉鉄道は、木炭動車や蓄電池動車をかき集め、貨車の間に挟んで走らせた。とにかく人と物を動かすしかなかった。
一番の繁忙期は昭和19年。工業地帯・芦原橋から南津守の倉庫群、そしてコンクリ桟橋へ。昼も夜も、木炭の煙をあげた列車が走り続けた。
石灰、石炭、硫黄、機械部品、弾薬、乾パン……そして、軍靴を履いたままの冷たくなった身体までも。
「貨物ヤードは、もうね、埋もれて見えんぐらいやった。パレットも、台車も、アリの巣みたいに動いてた。」
そう語るのは、釜ヶ崎のホームにいる老人。かつては害吉鉄道の貨物係だったという。
戦後、貨物輸送の波は引き、代わりに“労働者”が貨物のように運ばれるようになった。日本各地から大阪ユニオン駅に降り立った貧しい者たちは、107号に揺られ、釜ヶ崎のバラック街へと向かった。今もそれは続いている。
「なあ、あの動力、いつ止まるんや?」
「止まらんよ。止めたら、ここら一帯が死んでまう。」
白煙をあげ、木の香と炭の匂いを撒き散らしながら、107号は走り続ける。旅客も貨物も、何もかもごちゃまぜにして。
ここは害吉鉄道。時代に取り残された鉄路の、最前線だ。