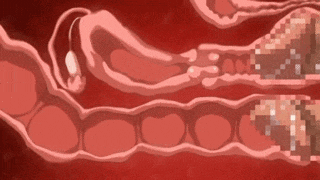ウンコう日誌(第753号)

害吉鉄道の釜ヶ崎支線。その終点にぽつんと佇む木造の小駅「南中市場前駅」には、今や動く列車がほとんど来ない。だが、日が昇る前、まだ路地に酔客の影が残るころ、小さな振動とともにカタコトと現れるのが「107号蒸気動車」である。
107号は、かつて大阪民国の中心部で活躍していた小型の路面蒸気動車だった。木炭をくべて動くその姿は、戦前のモダンを今に伝える生きた遺物。今では貨物扱いのついでに、地元住民を数人乗せて走る“ついで列車”である。釜ヶ崎からコンクリ桟橋まで、朝の一往復だけ。
運転士の金山は、五十を過ぎても制服の袖に油のしみを絶やさぬ男だ。かつては本線のC53を振り回していたというが、いまやこの古臭い車両が彼の世界のすべてになっていた。
駅の片隅にいる老婆が一人、毎朝107号に乗る。行き先はいつも「コンクリ桟橋」だが、何をしに行っているのか誰も知らない。ただ、彼女が降りるときには必ず運転席に缶コーヒーが1本置かれている。無言のやり取り。たぶん、もう何年も続いている。
蒸気の吐息とともに、車体がぎこちなく動き出す。駅の片隅で煙突から立ちのぼる煙を見上げながら、若い日雇い労働者が一人、缶ビール片手にぼそっと呟く。
「まだ走っとんのか、これ……」
⸻
害吉鉄道の朝は、こうして始まる。錆びたレールの上で、時代に置き去りにされた107号が、また今日も走る。コトン、カタン。昭和の残響とともに。