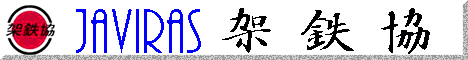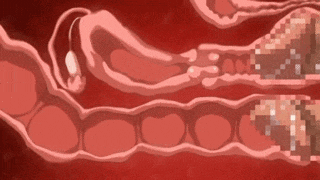ウンコう日誌(第751号)

大阪民国・芦原橋。まだ空も白みきらぬ午前4時半。コトン……コトン……と、乾いたリズムで目を覚ますのは、害吉鉄道の木炭動車107号車。戦前に製造され、戦後の混乱期に台湾から戻され、いつしかこの多民族都市の片隅に流れ着いた。
107号車は、朝焼けの釜ヶ崎支線を走る。乗客は、眠たげな目をこすりながら積み荷の上に腰かける労働者たち——沖縄から、奄美から、済州から、そしてアジアのさらに南から来た民工たち。日雇いの現場へ向かう彼らを乗せ、かつての遊郭地帯をすり抜け、朝霧にけぶるドヤ街へと滑り込む。
木炭の煙は、エンジンの上から細く立ちのぼる。この煙は、107号の心臓の鼓動だ。戦後すぐはどの地方都市にもあった木炭車も、いまやこの害吉鉄道の一両のみ。ディーゼル燃料が入らなくなった時期、何度も火を絶やしそうになりながらも、釜ヶ崎の炭屋が薪を届け続けたという。
駅には、名もなき男が腰かけている。誰かを待っているのか、何かを諦めたのか。それでも列車は止まらない。時代がどうあれ、木炭を焚けば走る。今日もまた、誰かをどこかへ運ぶ。それが107号の仕事だ。
そして夕暮れには、再び煙をくゆらせながらコンクリ桟橋へと向かう。荷台に積まれているのは、釜ヶ崎で売れ残った弁当、リサイクル品、そして国籍不明の旅人ひとり。
——この列車は、時代から取り残されたのではない。時代が通り過ぎていったのに、彼だけが誰も見ていなかったものを、今なお運び続けているのだ。