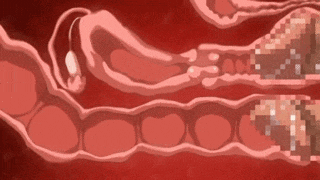ウンコう日誌(第827号)

その機関車は、どこか言葉を失ったような顔をしていた。
黒い塗装はくすみ、煙室扉の赤いナンバープレートは擦り切れている。
よく見れば、番号は日本式の「D51」だが、どこか字面が歪み、
現地で付け替えられたようなД51の影を残していた。
かつてこの機関車は、樺太の奥地を走っていた。
森林鉄道でも、炭鉱専用線でもない。
「とりあえず線路があるところを走らされる」存在だった。
終戦の年、彼女は南へ送られた。
引き揚げ列車の先頭に立ち、人も荷も、国境も記憶も引きずって。
港での積み替え作業の混乱の中、
誰かがチョークで書いたのが、煙室横の小さな文字だった。
Д51
それは管理番号でも、落書きでもなかった。
「ここから先は日本じゃない」
「でも、帰る先ももう日本じゃない」
そんな境界線の記号だった。
⸻
大阪民国・害吉鉄道の構内。
青いプラスチックのレールの上で、Д51は今日も短い貨物を牽いている。
後ろに繋がるのは、雑多な積荷と、古い詰所の模型。
コンクリ桟橋へ向かう途中の、仮の停泊だ。
詰所の前で、作業員たちが煙草を回している。
「おい、このカマ、えらい渋い顔しとるなぁ」
「そらそうや、あいつ樺太帰りやで」
「は? サハリン? マジかいな」
「マジマジ。ロシア語も聞こえる言うとったわ」
別の男が、機関車の側面を軽く叩く。
「お前、分かっとるか。ここは大阪民国や」
「日本ちゃうし、ソ連でもないで」
「まぁ…どこでもええか」
Д51は何も答えない。
ただ、かつて氷点下で凍りついたピストンの感触を、
今もロッドの奥に覚えている。
⸻
夜。
大阪ユニオン駅から流れてきた労働者たちが、
コンクリ桟橋行きの列車に乗り込む。
ベトナム語、広東語、朝鮮語、大阪弁が入り混じる。
「형님, 이 기차 안전한 거 맞아?」
「知らんけど、走るやろ」
「走らんかったら、押したらええねん」
「哈哈,真是大阪」
発車の合図。
Д51は低く息を吸い、ゆっくりと動き出す。
彼女はもう、どこの国の機関車でもない。
樺太でも、日本でも、ソ連でもない。
境界線の上を走る鉄の塊だ。
それでも――
線路がある限り、荷がある限り、
そして「行き場のない人間」がいる限り。
Д51は走る。
誰かがぽつりと言った。
「このカマな、帰ってきたんやなくて」
「流れ着いたんやと思うわ」
その言葉だけが、
蒸気の音に紛れて、妙に正しかった。