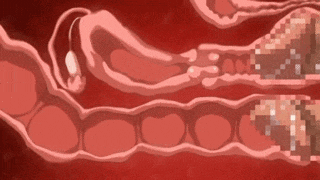ウンコう日誌(第823号)

天塩炭鉱鉄道で「社型C58」と呼ばれていたその機関車は、もともと炭鉱主の見栄と技術者の意地が生んだ存在だった。
国鉄がようやくC58を量産し始めた頃、天塩の炭鉱会社は「待っていられない」と判断し、国鉄設計をほぼそのまま写した図面で、自前の工場にC58を造らせた。石炭と鉄と人手は潤沢だった。国に頼らず、国と同じものを持つ。それが炭鉱の誇りだった。
やがて炭鉱は閉じ、線路は剥がされ、社型C58は長いこと倉庫の奥で眠った。
そして数十年後、誰の因果か、大阪民国の害吉鉄道に流れ着く。
害吉鉄道に来た初日、機関庫前で社長――自称「鉄道帝」――が満足げに眺めて言った。
「ほぉ……私鉄のC58やて。ええ趣味しとるやないか」
整備員の一人が油まみれの手で頬を掻きながら返す。
「社長、こいつ国鉄モンと寸法は一緒ですけど、中身ちょいちょい違いますわ。北海道の炭鉱仕様や。寒冷地前提です」
「かまへんかまへん。大阪は人間の方が寒がりや」
そう言って笑ったが、社型C58は黙っていた。
煙突も、動輪も、ここがどこかなど気にしていない。ただ与えられた線路を走るだけの鉄の塊だ。
初仕事は、大阪ユニオン駅から芦原橋を経て、コンクリ桟橋へ向かう貨物列車だった。
コンテナには雑多な荷物。工具、古着、謎の機械部品。人も少し混じる。
ホームで待つ労働者たちの声は、もはや言語の境界を失っている。
「おい兄ちゃん、这车去コンクリ码头吗?」
「아, 맞다 맞다. 콘크리까지 간다」
「ほな乗りや、立っとる場所あぶないで」
社型C58は、天塩の雪ではなく、大阪の湿気を肺いっぱいに吸い込み、黒い煙を吐いた。
石炭の質は悪く、火床は落ち着かない。それでも動輪は確実に回る。
芦原橋の手前、本社前の小さな停車で、運転士がぽつりと言った。
「こいつ、ええ機関車やな。炭鉱モンは根性ある」
助士が笑う。
「根性て。鉄の塊ですやん」
「ちゃう。使われ方や」
社型C58は、天塩では石炭を運び、ここでは人と荷を運ぶ。
支配も帝国も関係ない。ただ線路の先が仕事場だ。
やがて列車はコンクリ桟橋に着く。
海の匂い、錆びた鉄、外国語の怒号。
天塩の炭鉱とは正反対の世界だ。
それでも社型C58は止まり、蒸気を抜き、次の発車を待つ。
国鉄でもなく、炭鉱鉄道でもなく、今は害吉鉄道の機関車として。
誰もその来歴を気にしない。
だが、動輪の奥には、かつて「私鉄がC58を造った」時代の矜持だけが、まだ熱を持って残っていた。