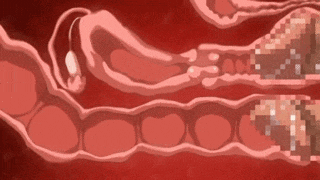ウンコう日誌(第816号)

コンクリ桟橋の朝は、海から吹く油じみた風と、どこの国の言語ともつかない怒号で始まる。そこにひょこ、と鼻先を出したのが——害吉鉄道の蓄電池動車《アシッド907》。
車体は濃い緑と薄い緑のツートン、鼻先には、いつ誰が付けたのか分からない巨大な排障器。元々は大阪民国の軍港で弾薬運搬をしていたが、戦後の混乱で用途を失い、バッテリーだけが取り替えられながら「生き延びてきた」時代遺物である。
◆
その《907》のドアがガコン、と開くと、ホームにいた荷物担ぎの男が叫んだ。
「おいおい、また電池切れ寸前ちゃうやろな!? いまから北津守まで満載やで!」
車内から、ごつい帽子をかぶった車掌が顔を出した。
「だいじょぶや、兄ちゃん。ほら見てみ、ちょっとは充電したんや。……ちょっとだけな」
「ちょっとだけて! ほな途中で止まったらどないすんねん!」
「押したらええやん」
「どこの国の鉄道が蓄電池動車押して走らすねん!?」
◆
アシッド907は、害吉鉄道の中でも「もっとも気まぐれ」という不名誉な称号を持つ。
理由は簡単で、蓄電池の気まぐれと、モーターのご機嫌が一致することが滅多にないからだ。
だが、その気まぐれさこそが、コンクリ桟橋に流れ着いた人々——琉球から、鮮から、南洋から、そして貧しい日本列島各地から渡ってきた労働者たち——の心に妙な親近感を抱かせていた。
「ワシらも気まぐれに流されて来た身や、乗り物も同じやと落ち着くわ」
と誰かが言い、
「途中で止まっても、まあええか、ここも大阪民国やし」
と誰かが笑う。
◆
その日の907は、珍しく調子がよかった。
芦原橋(本社前)を出て、釜ヶ崎支線への分岐を過ぎ、北津守へと滑るように走り出す。
だが、コンクリ桟橋手前——。
「……兄ちゃん、なんか焦げ臭ない?」
「うわ、ほんまや、またモーター焦げとる!」
「いやでも走ってるし、セーフやろ」
ガタガタガタガタ——。
907は最後の力を振り絞るように、桟橋の手前の勾配を登る。
車内の労働者たちは、左右の窓から吹き込む潮風を胸いっぱいに吸い込んだ。
「ああ……大阪ユニオンより混沌で、堀江新地より騒がしくて、
世界全部がここに流れて来る匂いや……」
やがて、電池が切れかけた音がした。
ピー……。
「止まるぞおおお!!」
運転士の叫びと同時に、907はギリギリのところで停車した。
ちょうど、桟橋の荷役用クレーンが見える位置だ。
「到着や! ……たぶん。」
乗客たちは笑いながら降りていく。
907は黒煙こそ出さないが、車体全体で「ふう……」とため息をついたように見えた。
◆
その日の夕方、芦原橋の車庫に戻ってきた907は、整備士に言われた。
「おまえまたよう頑張ったなぁ……ええ子やで」
すると、車体のヘッドライトが、ほんの少しだけ明るく点いた。
まるで嬉しそうに、誇らしげに。
害吉鉄道において、蓄電池動車907は決して主力ではない。
速くもなく、強くもなく、すぐへばる。
だが、
「流れ着いた者を運ぶ」
という一点において、誰も907の代わりはできなかった。
今日もまた、世界のどこかから漂着した荷物と人生を乗せ、
《アシッド907》は青い軌道の上を、ちょこちょこと揺れながら走っていく。
その姿は、大阪民国という巨大な混沌の象徴そのものだった。