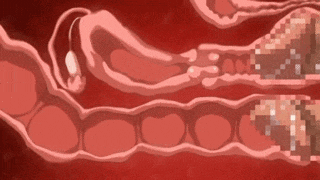ウンコう日誌(第799号)

害吉鉄道・大阪ユニオン駅構内。
煙を上げず、静かに青いレールの上に鎮座する黒い機関車。そのナンバープレートには「C58 254」、そして赤いヘッドマークには「天塩」の二文字。
もとは北の果て――天塩炭鉱鉄道。
戦後間もなく、石炭を積んで走り続けた鉱山鉄道の英雄。
だが、炭鉱が閉じ、人も街も消えた時、彼女は仲間のC11や9600たちとともに“解体線”へ送られるはずだった。
そこに現れたのが、害吉鉄道の社長であり、自称「鉄道帝」。
彼は言った。
「蒸気が消えた国など、国ではない。天塩の娘、わしが引き取る」
こうして社型C58は、貨車2両とともに大阪民国へと送られた。
芦原橋の闇市を抜け、釜ヶ崎を越え、コンクリ桟橋の空の下まで。
貨物列車に紛れ、煙を吐かぬよう息を殺して走るその姿は、まるで異郷に流れ着いた亡命者のようだった。
いま、社型C58は害吉鉄道の「北津守〜南津守」間で、夜間貨物を牽いている。
石炭はもうない。積んでいるのは、古い機械、アルミ屑、そして釜ヶ崎へ帰る労働者たち。
誰もその汽笛を聞くことはない。
代わりに、車体の奥から、かすかな風音のような唸りが響く。
「ボイラーは冷えたけどな……まだ、走れるよ」
かつて北の凍土を駆けた機関車は、今、南の熱気の中で第二の生を生きている。
その車体に残る「天塩」の文字だけが、彼女が北の生まれであることを静かに語っていた。