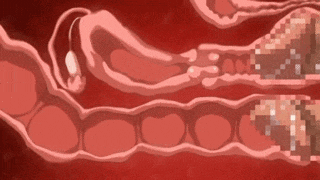ウンコう日誌(第796号)

害吉鉄道の車庫の奥で、誰にも見向きされず眠っていた緑の小型蒸気動車――通称「阿倍野のモクモク号」が、ひさびさに煙突を黒々と光らせていた。
鉄道帝の気まぐれで、芦原橋(本社前)〜釜ヶ崎支線の臨時列車に抜擢されたのだ。
「おーい、煙が逆流してんで!」
車庫係のベトナム人整備士タインが、油まみれの手ぬぐいで顔をぬぐった。
屋根の上ではミャンマー出身の青年整備士が、竹棒で煤をつつき出している。
車内には大阪弁、クメール語、タガログ語が入り乱れる――これが大阪民国の現場の日常だ。
芦原橋の構内では、煙を吐きながら出発準備をする107号を見て、釜ヶ崎の労働者たちが笑った。
「なんやこのチンチン電車みたいなん!」
「けどエンジンの音ちゃうで、ポンポン言うとる!」
まもなく、「モクモク号」は鈍い笛を鳴らして動き出した。
客席の隅では、朝鮮から渡ってきた若者が、古い紙袋を抱えて座っていた。
「堀江まで行けるんか?」
「行けるっちゃ行けるけど、煙で窓あけたら顔まっくろなるで」
運転士が笑って言うと、車内の乗客全員がどっと笑った。
この鉄道では、いつも笑いと油と煤が混ざり合っている。
夕方、釜ヶ崎駅のホームに着いたとき、蒸気動車の車体はすっかり黒ずみ、屋根の上ではまだ湯気が立っていた。
駅の片隅では、古びた木造の詰所の前で、一人の老人が腰をかけて煙草をふかしていた。
「おまえ、まだ動くんか……。わしが若いころ、これで堀江まで行ったんやぞ」
老人の声に応えるように、107号はボッ……と最後の白煙を吐いた。
その煙は夕焼けに染まりながら、芦原橋の方角へと流れていった。
――時代遅れの車両が、まだ大阪の片隅で息づいている。
害吉鉄道では、機械も人も、時代に取り残されてなお、今日も走り続けているのだ。