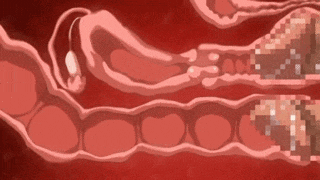ウンコう日誌(第795話)

害吉鉄道・芦原橋本社前。夕暮れのヤードに、黒く煤けたC56形が静かに止まっていた。
機番は「C56160」。そのナンバープレートの下には、小さく「かばちゃエクスプレス」と書かれた札。だが誰もその由来を知らない。
この機関車は、かつて泰緬鉄道を走った帰還機だった。ジャングルの湿気と赤土をまとい、戦後の混乱の中で故郷・大阪へ戻された。いまは害吉鉄道の“貨客混載”列車を引いて、ユニオン駅からコンクリ桟橋へ、あるいは芦原橋を経て釜ヶ崎まで、日々の労働者を運ぶ。
石炭はもう贅沢品だ。燃料は木炭、時には拾い集めたコークス。運転士の周鉄明チョウ・ティエミンはベトナム帰り、機関助士のラーマンは南インドの港町出身。
二人の言葉は半分大阪弁、半分ピジン。
「兄さん、今日もえらい煙やで」
「煙な、魂や。機関車まだ夢見てる」
ラーマンの言葉に、周は苦笑する。確かにこのC56には魂が宿っている。夜になると、密林の猿の声が聞こえると整備士たちは言う。
客車には、芦原橋の露店で仕入れた雑貨、荷台の上には旅装束の人々。屋根にまで人が乗っている。
行先は「コンクリ桟橋」——そこには世界中の漂流者が集まる。アジアのラゴス、大阪民国の果て。
発車ベルが鳴る。
「害吉六番線、かばちゃエクスプレス、コンクリ桟橋行き、発車しまーす!」
黒煙を噴き上げてC56160は動き出す。
錆びた動輪が唸り、ピストンがリズムを刻む。
屋根の上の男が叫ぶ。
「走れ、黒い花嫁! 地獄をくぐった鉄の娘や!」
誰もが笑った。
そして、その笑い声に混じって、泰緬のジャングルを吹き抜けた風の音が、確かに聞こえた。