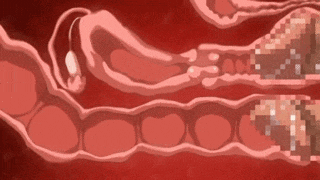ウンコう日誌(第794号)

害吉鉄道・芦原橋(本社前)駅の片隅。
灰色の空の下、木炭動車107号は、今日も煙突から薄く白い煙を吐き出していた。ディーゼルカーが主力となった今、木炭動車の姿は珍しく、整備工場でも「よう動いとるなあ」と言われるほどの老体である。
運転士の老金(オ・グム)は、帽子を目深にかぶりながらぼそりとつぶやいた。
「107号、今日も釜ヶ崎まで頼むで」
客は三人。
コンクリ桟橋から流れ着いた労働者、芦原橋で降りる日雇い、そして釜ヶ崎へ帰る古びたラジオを抱えた老人。
彼らを乗せ、107号は青い線路の上を、ぎこちない音を立てて走り出した。
車内には、かすかに木炭の匂いが漂う。
昭和の残り香のようなその匂いは、どこか懐かしく、そして哀しい。
「なあ、兄ちゃん。この列車、まだ木炭で走っとるんか」
「せや。ガソリンも電気も高うてな。木炭のほうが安いんや」
そう言いながら老金は、炉の中に黒い炭を足した。ぱちん、と火花が散る。
窓の外には、崩れかけた倉庫、海鳥の影、そして遠くに見えるコンクリ桟橋。
桟橋には、今日も船が着き、異国の労働者が降り立つ。
だが、彼らを迎えるのは夢ではなく、現実の重さであった。
「――あの桟橋、昔は光っとったんやけどな」
ラジオの老人が、ぽつりと呟いた。
「戦後すぐは、人がようけ働いとった。夢を見てた。けど、気づいたら誰も笑わんようになってしもうた」
木炭動車107号は黙ってその声を聞いていた。
古びたボディの奥、鉄の心臓はまだ鼓動を打っている。
それでも、時代の波は確実にこの列車を取り残していく。
釜ヶ崎のホームに着くころ、日はもう沈みかけていた。
ホームの片隅には、夕食の匂いと、人のぬくもり。
老金は軽くハンドルを叩き、107号に囁く。
「今日もよう走ったな。お前が止まったら、この街も止まるんや」
煙突から、細く白い煙がまたひと筋。
107号は、それに答えるように微かに震えた。