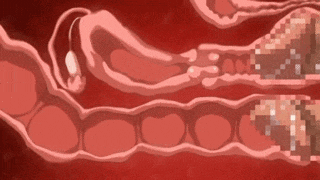ウンコう日誌(第792号)

緑の蓄電池動車は、今日も静かにホームを離れた。
パンタグラフも煙突もないその車体は、夜の街のざわめきの中に溶けていく。
車掌は片手義手の老婆。かつて「電気の娘」と呼ばれた蓄電池職工で、車内では今も古い歌を口ずさむ。
♪どこへ行くのか この街は
♪煙と鉄と 人の夢
終点は釜ヶ崎。
駅舎の灯りは薄く、看板には「芦原橋(本社前)」と手書きで書き足されている。
車体の側面には、油で黒ずんだ数字――107。
この車両は、害吉鉄道の創業期にたった三両だけ造られた“蓄電池動車”の最後の生き残りだ。
「今日は、コンクリ桟橋からの労働船が遅れとるで」
老婆は鼻で笑いながら、義手でブレーキを軽く撫でた。
「電気が切れる前に、釜まで届けなあかん」
乗客は三人。
ベトナム語を話す青年、韓国から来た女工、そして日本語が片言の子ども。
誰もが疲れきった顔をしているが、窓の外のネオンの川を見つめながら、それでも小さく笑っていた。
車両はやがて、南津守のトンネルに差しかかる。
そこは、かつて蓄電池を盗まれたという曰く付きの区間。
「また電気、吸われるかもしれんなあ」
老婆はそう言って、ポケットから古い手回し式の懐中電灯を取り出した。
キイ、キイ、キイ。
光は揺れ、まるで古い心臓が拍動を思い出したかのように、車内を照らした。
やがて、列車は終点に着いた。
釜ヶ崎の夜風の中、老婆はひとり降り立つ。
車体の側面から、微かな唸りが聞こえた。
――まだ走れる。
そう言っているようだった。