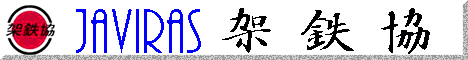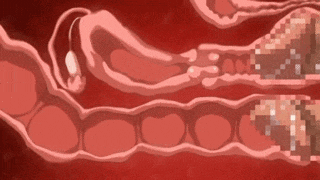ウンコう日誌(第789号)

戦後の混乱期、大阪民国の港・コンクリ桟橋に、錆びた貨車を曳いて一台の黒い蒸機が流れ着いた。
その名は「Д51」。ソ連式の銘板を残したまま、樺太の凍土を越えてきた“亡霊機関車”である。
「オレ、もとは北海道のD51や。けど、終戦後に向こうの軍に接収されてな、ロシアの雪原を走っとったんや。」
そう語るように、煤けた車体のあちこちにはキリル文字のペンキ跡が残り、煙突には氷解剤の白い痕がこびりついている。
害吉鉄道は、そんな彼を“拾って”しまった。
整備主任の李スーヨン曰く、「日本の部品もソ連の部品も合わへんで、どっちもガタガタやけど、動くのが奇跡や」と。
動輪は片方がミリ規格、もう片方がインチ規格。炭水車は樺太時代に改造され、燃料は石炭でも木炭でもディーゼルでもない、「なんか黒いもん」だった。
それでも、害吉鉄道は彼を貨物兼旅客の列車に組み込んだ。
コンクリ桟橋から釜ヶ崎へ、世界中の労働者を運ぶために。
客車には各国の言葉で「乗るな」「押すな」「降りるな」と書かれており、屋根には荷物と人が同居している。
夜、芦原橋(本社前)での停車中。
D51はふっと小さな吐息をついた。
「樺太の夜は、もっと冷たかった。でもな、こっちは温(ぬく)い。人間の叫び声で、空気が生きとる。」
彼のボイラーの奥で、まだ凍てついた樺太の風が鳴っている。
それでも彼は今日も、青いレールの上をゆっくりと転がる。
次の停車駅は、釜ヶ崎。
世界の片隅で、まだ誰かを運ぶために。