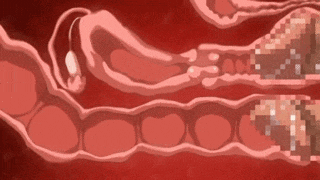ウンコう日誌(第779号)

大阪民国の片隅、害吉鉄道のヤードに眠っていたのは、古びた緑色の蓄電池動車だった。
形式名すら曖昧なまま、ただ「バッテリーカー」と呼ばれ、誰からも忘れ去られた存在。しかし夜になると、この車両は低い唸り声とともにゆっくりと走り出す。車内にあるのは座席ではなく、大量の鉛電池。貨物輸送の名目で造られたが、実際は釜ヶ崎に流れ込む日雇い労働者を密かに運ぶ「闇の列車」だった。
昼間は駅の片隅の小屋で、人々は煙草をふかしながらこの車両を待つ。
「おう、今夜も走るんか?」
「走るさ。あの音が聞こえたら、釜ヶ崎行きや」
やがて電池の匂いをまとい、動車は静かに発車する。ディーゼルカーのような轟音も、蒸気機関車のような白煙もない。ただ低くうなるモーター音と、わずかな火花が線路を照らすだけ。
コンクリ桟橋から流れ着いた移民労働者、ユニオン駅で日雇いを終えた男たち、酒瓶を抱えた老人――誰もが車内で無言のまま揺られている。蓄電池動車は、彼らの小さな「隠れ家」だった。
しかし社長・鉄道帝はこの車両に別の野望を抱いていた。
「石炭も石油も要らん、新時代の鉄道や! 大東亜の夜を、この静かな電池車で征服するんや!」
そう豪語するが、車両はひどく老朽化し、電池はしょっちゅう切れる。釜ヶ崎まで辿り着けず、途中で停まってしまうこともしばしば。そのたびに乗客たちは笑いながら押してやるのだった。
――誰の夢も叶えない、しかし誰もが利用する。
そんな時代遅れの動力車は、今日もまた夜の街を静かに進んでいく。