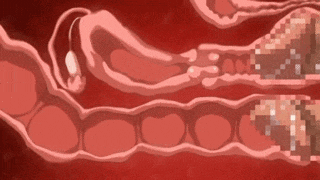ウンコう日誌(第747号)

大阪民国・北津守駅の片隅。半ば打ち捨てられたようなホームに、緑の蓄電池動車「107号」は、無言のまま停車していた。
この車両は、かつて内地の軍需工場で構内輸送に使われていたが、戦後に払い下げられ、各地を転々とした末、ついに害吉鉄道に拾われた。騒音も煤煙も出さないその静けさは、害吉の喧騒には不釣り合いとも言えたが、それゆえに、ある意味「異物」として残ることを許されたのかもしれない。
昭和の残り香が漂う堀江新地から、南津守のコンクリ桟橋へ。この107号は、一日2往復だけ、路地裏のような支線を走っている。乗客は少ない。ほとんどが釜ヶ崎の年寄りや、東南アジアから来た清掃労働者たちだ。
車内には暖房も冷房もないが、天井の扇風機だけが回る。バッテリーの残量を気にしながら、運転士は速度を抑えて走る。沿線には、廃タイヤと犬と子供の姿。鉄道の未来でも過去でもない、奇妙な「横すべりの現在(いま)」がそこにあった。
ある日、乗車していたラオス出身の青年が、何気なく言った。
「この電車、音がしないから…神さまが乗ってる感じする」
それを聞いた車掌は、しばらく黙ったあと、ぽつりと答えた。
「この車両な、昔は『無尽機関』いうて呼ばれてた。燃料も煙もいらん、ただ走るだけの機械や。けどな、走る理由を忘れたら、それはただの箱や」
青年はわかったようなわからないような顔をして、車窓の外を見つめた。
そして今日も、107号はゆっくりと、しかし確かに走る。音もなく、けれど確かに、害吉鉄道の片隅で――時代の境界を、静かに滑り続けている。