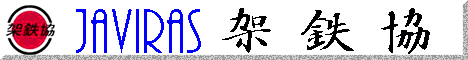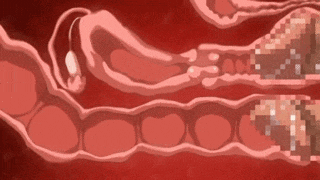ウンコう日誌(第742号)

害吉鉄道・南津守貨物ヤード。
焼けたコンクリートの照り返しの中、CK285形蒸気機関車が静かに息を潜めていた。かつて台湾の平渓線で山岳貨物を引いていたこの黒き老機関車は、今では害吉鉄道に籍を置き、「焼酎特急・黒潮号」として再び現役に返り咲いている。
今日の任務は、奄美・笠利港からフェリーでコンクリ桟橋へ運ばれた「奄美黒糖焼酎」の陸送だ。黒潮号は黒光りするタンク貨車を2両従え、北津守の精製所を経て、最終的には釜ヶ崎の裏市場へと運び込むのだ。
「シュッ、シュッ、シュッ…」
機関士は老齢の華僑出身の男、名を張富勝(チョン・フゥシェン)という。戦後、国共内戦を逃れて大阪に流れ着き、それから半世紀、機関士一筋でやってきた。相棒は沖縄系三世の少年・知念まこと、まだ14歳。師弟のような関係で、まことは機関士見習いとしてボイラーの火を守る。
「老師(ラオシー)、北津守まで何分ですか?」
「勘で言うと……四十七分。でも害吉は線路が歪んでるから、信用したらあかん。」
車体がガタンと揺れた。芦原橋のスイッチバックだ。ここで進行方向が変わる。機関車を転線させるのではなく、操車場の人夫たちが人力で貨車を押し、向きを切り替える――いまだにそんな運用がまかり通る鉄道、それが害吉鉄道である。
途中、釜ヶ崎駅では飲んだくれの男たちが手を振る。
「おおい!焼酎、焼酎ぅ!そいつこっち持ってこいや!」
「こら黙っとけ、こいつは納品用じゃ。お前らの分は明後日の残酒便で回すから、寝てろ!」
張富勝が怒鳴ると、男たちは笑って引き下がった。害吉鉄道では、乗客も労働者も、酒も煤も、すべてがごちゃまぜで共存している。
⸻
終着・南津守駅。
夕暮れ、焼酎タンクが一つずつ降ろされていく。タンクには「笠利蒸留所謹製」とある筆文字が浮かぶ。黒潮の彼方、奄美の島影から遥々と。
CK285は、再び黙して次の出番を待つ。その側面には、剥がれかけた台灣鐵路管理局の銘板が、いまでも誇らしく残っている。
彼女はもう、日本のどの鉄道にもいない。しかし、害吉鉄道では現役だ。黒糖焼酎の匂いを煤とともにまといながら、今日も大阪民国の片隅を走り続けている。