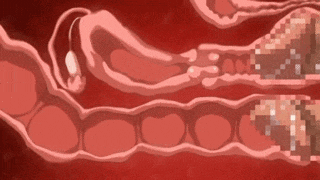ウンコう日誌(第741号)

コンクリ桟橋駅には、世界中の雑踏と油煙が絡み合っていた。重油とパクチーと香辛料、そして潮風。干物屋の廃材を組み直したような屋台の奥で、男たちは黙って缶ビールを飲み、次の船便や仕事の噂話をしていた。
そのホームの一角に、くすんだ水色の車体が静かに停まっていた。キハ40。古びたディーゼルカー。正面の丸いプレートには、かろうじて読める字で「働かせてください」と書かれている。
この車両は、かつて八戸の港を走っていた。イカ釣り漁の季節になると、夜明け前から魚の脂の匂いが染みついた乗客たちを、岸壁と飲み屋の間を結んでいた。女たちは頬を紅く染め、男たちは酔って歌い、車内には炭火焼きの匂いが満ちていた。
だが、時代が変わった。
再開発の波が港をさらい、キハ40は解体寸前だった。そこに目をつけたのが害吉鉄道の「鉄道帝」だった。八戸からコンクリ桟橋まで、気が遠くなるような迂回航送の末、この車両は大阪民国の片隅に流れ着いたのだ。
キハ40は、今や釜ヶ崎行きの列車として余生を送っている。芦原橋でスイッチバックを繰り返しながら、今日も重たい車輪を軋ませる。乗っているのは、クメール語を話す男、タガログ語で電話する女、耳の聞こえない老人、そして物言わぬ旅芸人。
彼らの目的地は、終点・釜ヶ崎。
仕事があるとは限らない。寝床があるとも限らない。それでも、列車は走る。潮の匂いをまとったまま、忘れられた世界の端をすべるようにして。
今日もまた、一人の男がぼそりと呟く。
「ここじゃなきゃ、生きられねえんだ」
キハ40は何も答えない。ただ、錆びたエンジンを咳き込みながら、釜ヶ崎へ向かって動き出した。