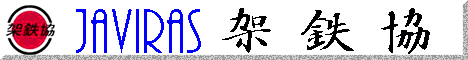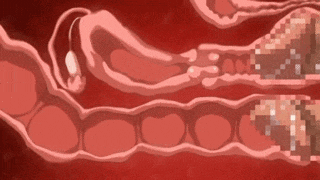ウンコう日誌(第738号)

大阪民国の片隅、時の澱がたまるような裏界路を縫いながら、蒸気動車107号はゆるりと息を吐く。害吉鉄道——かつて誰かが敷き、今では誰も整備していない鉄道。だが、その車両は今も走る。いつの世の鉄か定かでない蒼碧の双条の道を、節くれだった車輪が擦り寄ってゆく。
車体は苔むした緑、煙突は煤で艶を帯び、車窓には剥がれかけた旅路の記憶が貼りついている。乗客たちもまた、何かを運び、あるいは捨てに来た者ばかり。堀江新地から芦原橋、北津守、そしてあのコンクリ桟橋まで。誰に許可を取るでもなく、誰に迎えられるでもなく、ただ進む。
停車場の片隅、木造の待合所には「大阪芸術(華南口)」の名が褪せて残り、立ち尽くす女の背に風が吹いている。階段には果物の皮が落ち、行き先を知らぬ猫が柱の影にひそむ。そこでは、時間も国境も、声の届き方さえも不確かだ。
害吉鉄道に時刻表はない。運賃も改札も、ましてや駅員など存在しない。だが、誰かがいつかここに立ち、汽笛の音に振り向いたことだけは、どこかの壁に刻まれている。時代からこぼれ落ちた線路の、その上を、107号は今なお走っている。
この鉄道に乗るということは、昨日から遠ざかることでもあり、明日に触れようとすることでもある。だから、誰も乗らずとも、誰かのために今日も走る。——それが害吉鉄道であり、107号であり、第四世界の律法であった。