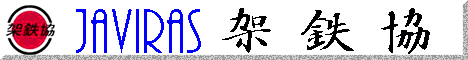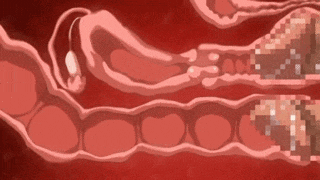ウンコう日誌(第737号)

朝のラッシュを少し過ぎたころ、C5343号機は堀江新地駅をゆっくりと発車した。漆黒の流線型ボディを誇る老蒸機は、今や害吉鉄道の象徴ともいえる存在だが、特別列車などではない。大阪民国の、いつも通りの“足”である。
牽引されるのは、半世紀以上前に製造された木造客車と、車籍不明の連接車。車体には各民族による落書きと装飾が混在し、屋根の上には洗濯物や野菜籠、子どもたちの笑い声まで載せられていた。
車内には言語が飛び交う。南津守語、鶴橋クレオール、港湾ウルドゥー――共通語としての関西弁が一応は使われているが、それも語尾が変則的だ。
「なあ、兄ちゃん。今日の市場、なんかえらい騒がしいらしいで」
「昨日な、堀江の浜でマグロが三尾あがったんやて。競りが揉めてたわ」
床には魚の箱が転がり、天井から吊られた金属網にはトウモロコシとミサンガがぶら下がる。乗客たちは荷物と体を器用に収めつつ、隣人の赤子を自然に抱き、老婦人に団子を分け合う。
鉄路はやや蛇行し、交差点では半ば手動で遮断機が降ろされる。芦原橋では一旦停車し、物売りと乗客が一斉に入れ替わる。
「うわ、また満員やがな……けど乗るわ。悪いな、おっちゃん、膝貸してえな」
笑いながら誰かがまたがり、C5343は重たく汽笛を鳴らす。
「ポォーーー……」
南津守の手前、築堤を登る列車からは遠くコンクリ桟橋の煙突が見えた。煙と潮のにおいが混じり合い、大阪民国の都市と農村と港湾が、一本の鉄路でゆるく繋がれているのがわかる。
時代に取り残されたのではない。
ここには、時代とは別の「今」が流れているのだ。
害吉鉄道は、今日も確かに、その「今」を運んでいる。