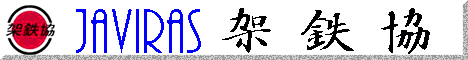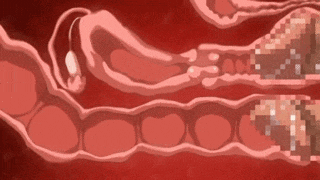ウンコう日誌(第688号)

害吉鉄道は、蒸気動車を保有する唯一の架空鉄道です。
ところで、なぜ蒸気があまり実用化されなかったのか、AIに聞いてみました。
蒸気動車(蒸気で走るレールカー)は、19世紀後半から20世紀前半にかけて世界各地で実用化されましたが、広範な普及には至りませんでした。
日本での蒸気動車
日本では、蒸気動車の導入例は非常に限られています。明治時代から大正時代にかけて、鉄道の発展に伴い、一部の私鉄や軽便鉄道で試験的に導入されました。例えば:
• 北海道の簡易鉄道:1920年代に一部の簡易鉄道で蒸気動車が試験的に導入されましたが、運用は短期間にとどまりました。
• 軽便鉄道:一部の軽便鉄道で試験的に使用されたものの、維持費や操作の複雑さからディーゼル動車や電車に取って代わられました。
世界での蒸気動車
海外では19世紀後半から20世紀前半にかけて、特にヨーロッパで実用化されました。
• イギリス:
• 19世紀末から20世紀初頭にかけて、蒸気動車が地方鉄道や支線で運行されました。代表例として「Sentinel steam railcars(センチネル蒸気動車)」があり、1920年代から1930年代にかけて英国や海外で使用されました。
• フランス:
• フランスでは「Chemins de fer de l’État」などで蒸気動車が導入され、一部は戦後まで使用されました。
• ドイツ:
• 「Wismar steam railcar(ヴィスマー蒸気動車)」などが開発され、短距離路線や地方鉄道で利用されました。
• アメリカ:
• 19世紀後半には、蒸気動車がローカル路線で試験的に使用されましたが、蒸気機関車のほうが一般的でした。
なぜ普及しなかったのか
1. 構造の複雑さ:蒸気機関はボイラーを搭載する必要があり、動車としての小型化が難しかった。
2. 維持費の高さ:頻繁なメンテナンスが必要で、運行コストが高かった。
3. 操作の難しさ:従来の蒸気機関車と同じように取り扱う必要があり、運転士の訓練が必要だった。
4. ディーゼルや電気の台頭:20世紀に入ると、ディーゼル動車や電車のほうが経済的であり、扱いやすいため、蒸気動車は淘汰されていった。
結論
蒸気動車は一部の国で短期間ながら実用化されましたが、技術的・経済的な理由から広く普及することはありませんでした。最終的にはディーゼル動車や電車に取って代わられました。