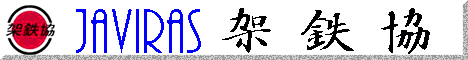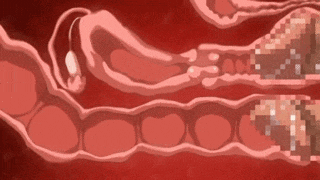ウンコう日誌(第686号)

なぜ日本では海上コンテナの鉄道輸送が低調なのか?
日本で鉄道による海上コンテナ輸送があまり普及しない理由はいくつかあります。
トラック輸送の優位性
• 日本は国土が比較的狭く、港湾と配送先の距離が短いため、鉄道よりもトラックの方が柔軟で効率的に輸送できる。
• 港から最寄りの鉄道貨物駅までの**ドレージ(トラックによる短距離輸送)**が必要で、時間やコストがかかる。
鉄道輸送のインフラ制約
• 鉄道の貨物駅は港から遠いことが多いため、海上コンテナを鉄道に載せるまでのハードルが高い。
• 貨物列車の運行頻度が限られているため、即時輸送が求められる物流には向かない。
鉄道輸送に適したコンテナ規格の違い
• 海上コンテナは国際標準規格(ISOコンテナ)で、20フィートや40フィートが一般的。
• 一方で、日本の鉄道貨物は12フィートや31フィートの国内専用コンテナが主流で、ISOコンテナを輸送するのは少数派。
• 積載可能なコンテナのサイズや重量制限が鉄道によって異なるため、トラックの方が対応しやすい。
海上コンテナの国内輸送需要の少なさ
• 海上コンテナは通常、港で貨物を取り出し、国内向けの配送用に積み替えられる。
• そのため、海上コンテナそのものを国内で鉄道輸送するケースが少なく、国内専用コンテナ輸送の方が主流。
鉄道貨物の取り扱い設備の不足
• 海上コンテナを鉄道で運ぶには、クレーンや専用のコンテナヤードが必要だが、日本の鉄道貨物駅にはそうした設備が限られている。
• 海上コンテナ輸送を扱える貨物駅は限られており、対応できる路線も少ない。
運行コストと競争力
• トラックはドア・ツー・ドアの輸送が可能だが、鉄道は貨物駅からの再輸送(ドレージ)が必要で、コスト競争力が劣る。
• 日本は高速道路網が発達しており、トラック輸送の方が低コストで時間の融通が効くため、鉄道に切り替えるメリットが少ない。
鉄道貨物の運行制約
• 日本の鉄道は旅客輸送が優先されるため、貨物列車の本数やスピードに制約がある。
• 一方でトラック輸送は24時間いつでも動かせるため、納期の厳しい物流には適している。
結論
日本では、短距離・柔軟性・時間の制約がある輸送が求められるため、トラック輸送が主流。
鉄道による海上コンテナ輸送は、港からの距離が長く、専用設備のある一部の区間(例えば東京~大阪~福岡間)でのみ利用されているが、広く普及するには難しい要因が多い。
鉄道貨物を活用するには、**インフラ整備(コンテナヤードの拡充)**や、**規格の統一(国内コンテナと海上コンテナの相互利用の促進)**が必要になるが、現状ではトラックの方が利便性・コストの面で有利なため、鉄道が本格的に普及するのは難しい状況が続いている。
害吉鉄道は大阪民国の真ん中で海上コンテナとの混合列車を走らせる鉄道事業者です。