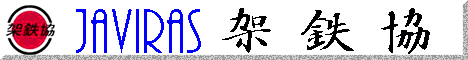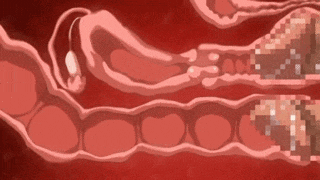ウンコう日誌(第684号)

「戦果アギャー」(せんかアギャー)は、琉球王国の物資不足の中で、戦争の残骸(戦果)を拾い集めて売る行為を指します。
交易品の変化
• 琉球王国はもともと、中国・東南アジア・日本などとの中継貿易を行い、織物、陶器、香木などを扱っていました。
• しかし、「戦果アギャー」が貿易の主体になると、武器、金属片、船の部品、廃棄された戦具などが主要な交易品となります。
• これにより、琉球王国は「戦争経済」に依存する可能性が高まります。
経済構造の変化
• 戦争が起こるたびに琉球王国の経済が活性化するため、戦乱地帯から物資を回収し、武器商人や鉄商人との取引が増える可能性があります。
• 逆に、平和な時期には収入が減少し、戦争が再開されると経済が回復するという不安定な構造になります。
政治・外交への影響
• 戦場跡から得られる物資を貿易に利用するとなると、琉球王国は戦争が起こる地域と密接な関係を持つようになります。
• 例えば、日本の戦国時代には、九州や中国地方の戦場から武器や鎧を回収し、それを東南アジアに輸出する形が考えられます。
• しかし、このような貿易は時の権力者の不興を買う可能性があり、戦国大名や中国の明・清王朝との関係が悪化する恐れがあります。
文化・社会への影響
• 琉球王国の人々が「戦果アギャー」を生業とするようになれば、技術的な発展が進むかもしれません。例えば、金属のリサイクル技術が向上し、新たな武器や工具が作られる可能性があります。
• しかし、戦場跡の物資を拾うという行為が常態化すると、労働力がそちらに流れ、農業や伝統産業が衰退するリスクもあります。
他国の干渉
• 「戦果アギャー」主体の貿易は、戦争を利用した経済活動であるため、武器や軍需品の取引が絡んできます。
• これは、例えば日本の幕府や清国に「危険な存在」と見なされる原因となり、琉球王国が武力介入を受ける可能性があります。
• 実際の歴史では、薩摩藩が琉球を支配しましたが、もし琉球が戦争経済に依存していた場合、より早期に征服されるか、別の列強国(オランダ、ポルトガルなど)が介入していたかもしれません。
結論
琉球王国が「戦果アギャー」を貿易の基盤とした場合、一時的に利益を得ることは可能ですが、戦争に依存する不安定な経済構造になり、長期的には政治的なリスクが増大します。特に、戦争を助長する要素があると見なされると、周辺の大国(明、清、日本)から圧力を受け、存続が困難になる可能性があります。
琉球王国は、実際の歴史では「平和外交」と「中継貿易」で繁栄しましたが、「戦果アギャー」路線を取ると、まったく異なる荒々しい歴史をたどることになりそうです。
害吉鉄道の阪琉航路の貨物線「戦果丸」。